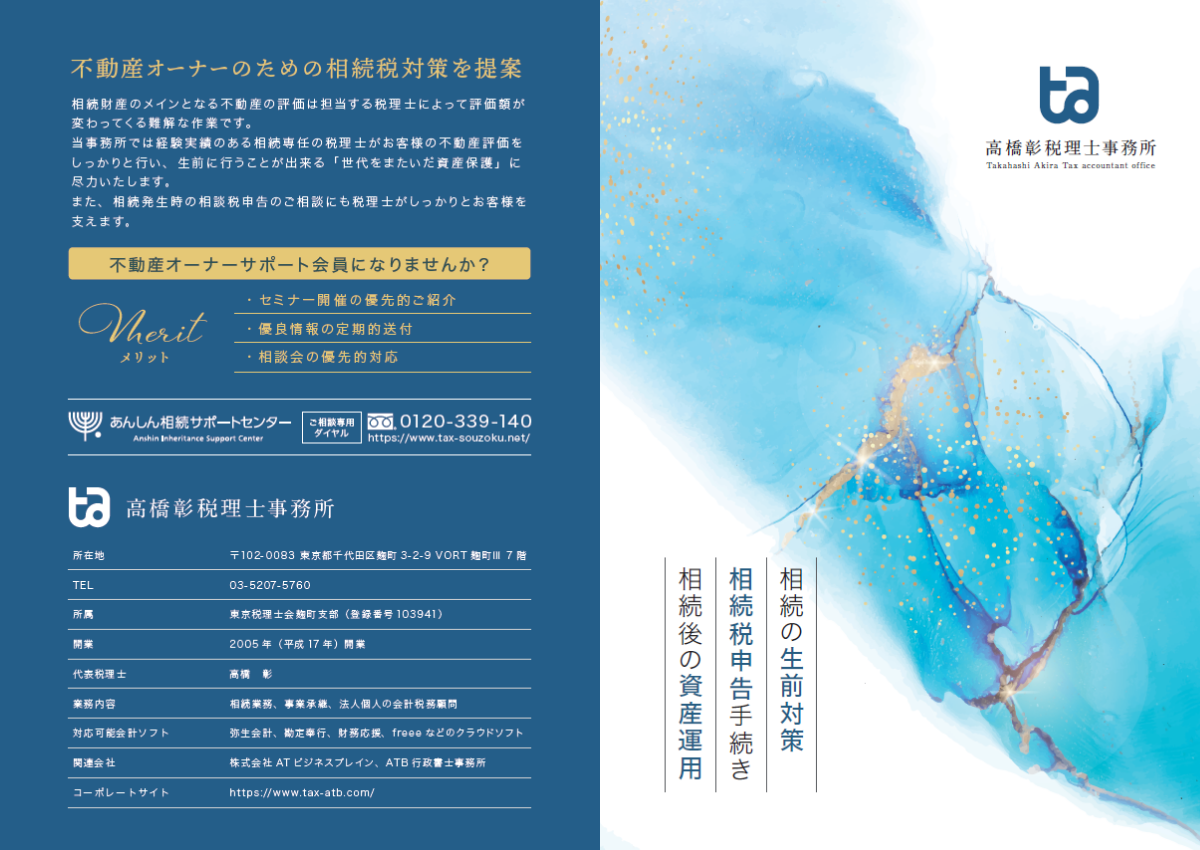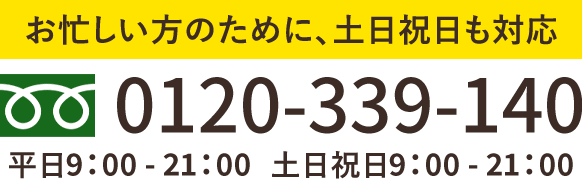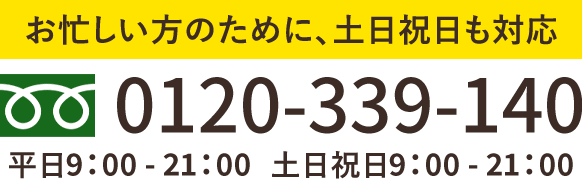相続税申告なら相続専門の税理士にお任せください|出張対象エリア(東京・神奈川・千葉・埼玉)
あんしん相続サポートセンターは高橋彰税理士事務所が運営しています。
相続専門の税理士に無料相談ができる
豊富な実績と専門知識で
相続税申告をもっと
節税しませんか?
名義変更、遺産分割手続き、相続税申告、納税対策まで、
分かりやすくご説明、まとめてご依頼ができます。
相続税申告なら相続専門の税理士にお任せください|出張対象エリア(東京・神奈川・千葉・埼玉)
あんしん相続サポートセンターは高橋彰税理士事務所が運営しています。
相続専門の税理士に無料相談ができる
豊富な実績と専門知識で
相続税申告をもっと
節税しませんか?


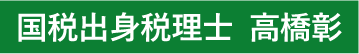
遺産分割手続き、
相続登記、
名義変更も対応
あんしん相続サポートセンターでは、相続に専門特化した税理士が
お客様の財産を次の世代にしっかり繋ぐため、専門家として
しっかり寄り添いサポートいたします。
相続手続きには、相続人の確定から遺産分割、年金や保険関係の諸手続き、相続税申告など
さまざまな内容が含まれます。しかも不備があればペナルティーが発生するケースもあり、
ミスは許されません。こうした手続きを税理士、弁護士、司法書士などそれぞれの専門家に
頼むと費用が高額になるだけでなく、やりとり自体も非常に面倒です。
お客様に煩雑な思いをさせず、私たちが相続手続きの窓口としてまとめてお受けし、
サポートするのが当センターのサービスです。
相続財産が基礎控除を超えそうで、相続税申告を依頼したい
相続登記や遺産分割協議もお願いしたい
次の二次相続も考えなくては...
まずはお気軽に無料相談から始めましょう。
相続手続きでお困りのお客様へ
-
うちには相続税がかかるの?
相続手続きで一番不安なのは、そもそも相続税申告が必要か、どれくらい相続税がかかるのかといった、相続税という税金の問題です。
「うちは相続税なんてかからないだろう」、そう思っても思わぬところでかかるのが税金の怖さです。
まずは相続税簡易シミュレーション(無料版)で概要を把握ください。さらに詳細をご希望の場合はお電話または「お問合せ」から面談予約(初回無料)が出来ます。どうぞお気軽にご連絡ください。
-
相続の手続きは誰に相談すればよいの?
相続手続きをどの専門家に相談したらよいか、誰に頼んだらよいか、お困りの方が多くいらっしゃいます。
私たちが窓口となって手続きをまとめてお受けし、他の専門家が必要な場合(例えば不動産登記変更が必要な場合は司法書士、遺産分割でもめている場合は弁護士など)は連携して、相続手続き全般をサポートしていきます。
もう迷わずに、安心してご相談ください。
-
相続手続きにはどんな書類が必要?
家族が急に亡くなって相続手続きをしないといけないが、何から手をつけていいか分からない、とお悩みの方も少なくありません。
遺産分割協議や相続税申告の診断を始めるためには、ご自宅で必要書類を集めていただくほかにも、公共機関、金融機関などでさまざまな書類を取得していただく必要があります。
ご相談時の際、一覧表をチェックし合いながら必要な書類をはっきりとさせていきます。加えて、それぞれの書類の集め方などもお話しできます。
ご自身で集めることがどうしても難しい場合は、私たちが代理委任を受けて対応することも可能です。
たとえ相続税申告が必要でない場合でも、預貯金の引出しや閉鎖手続き、不動産、有価証券の名義変更など、不慣れな手続きは本当に大変です。どうぞ、これらもお気軽にご相談ください。
-
税務署から送られてくる
「相続税についてのお尋ね」について相続税の申告と納税は相続から10ヵ月以内と決められていますが、その期間内に税務署から「相続税についてのお尋ね」が届くことがあります。税務署では死亡届出などで被相続人の死亡を把握しており、その中から絞った方に「相続税についてのお尋ね」を郵送しているためです。
書類が届いた方は本当にびっくりすると思います。
この文章が届いた方は是非とも、当センターにご相談いただき、申告の診断を受けられることをお勧めします。「相続税についてのお尋ね」の対応の仕方についてもご説明できます。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
私たち税理士には守秘義務が課せられており、秘密は守られますのでご安心ください。
専門家に
任せてあんしん
大切な家族が亡くなって途方に暮れており、複雑な相続手続きを行う気力も自信もない。葬儀、初七日、49日と続く中で、月日はあっという間に過ぎていきます。
・葬儀のお金は無くなられた方の預金から自由に引き出していいの?
・年金や 預貯金、有価証券の手続きはどうしたらよいのか?
・遺産分割はどうように決めていったらよいか?
・不動産の名義変更手続きはどうしよう?
・相続税申告は必要なのか?
・お金がない時に、相続税の納税はどのように対処したらよいのか?
これら全ての相続手続きについて、あんしん相続サポートセンターが窓口となってご相談、対応ができます。必要に応じて司法書士や弁護士などとの連携作業も可能ですので、どこに頼んだらよいか迷われる心配もありません。
相続税の申告は不動産の評価を中心にして、担当する税理士によって評価額、すなわち納税額が変わってくることがあります。また、今回の相続の遺産分割の仕方いかんで、次の相続(これを二次相続と言います)の税金の負担額が大きく変わる場合があります。
このように相続税の申告は「専門性の高い相続手続き」です。
あんしん相続サポートセンターでは、相続業務を専門とする経験豊富な税理士が業務を担当いたします。
どうぞ、あんしんしてご相談ください。
相続の専門家がしっかりとサポート
-


税理士高橋 彰
高橋彰税理士事務所の代表をしております。東京国税局に在籍後税理士として独立。調査にお困りの方はお気軽にご連絡ください。
-


税理士鈴木 勝博
法人、相続の双方の知識からお客様の状況に応じた、最適な相続対策のプランニングを、ご提案させて頂きます。
-


1級FP技能士
宅地建物取引士佐藤 悦朗信託銀行勤務の経験を活かしお客様目線の分かりやすい説明、親身な対応を心がけてまいります。遺言、信託などもお気軽にご相談ください。
-


中小企業診断士
科目合格者岩崎 巧相続でお困りの皆様にしっかりと寄り添い対応をさせて頂きます。専門用語を極力使わず、分かりやすい言葉でご説明させて頂きます。
-


司法書士津田 ミキエ
ご相談者に寄り添い、大切な不動産登記を親身に対応させて頂きます。長年の未登記の整理や家族信託などもお気軽にご相談下さい。
-


弁護士桝實 秀幸
遺産分割で、相続人間の意見がまとまらない、争いをなくし円満な相続をしたい、そんなお困りの方はどうぞご相談下さい。
-


司法書士小泉 純平
遺言や相続問題を中心に親切・丁寧をモットーに活動しております。日本で生活する外国人の方のために必要な法務手続きなども行っております。
税理士事務所のご紹介


運営事務所あんしん相続サポートセンター
株式会社ATビジネスブレイン
高橋彰税理士事務所
(所属:東京税理士会麴町支部)
住所〒102-0083
東京都千代田区麹町3-2-9
VORT麹町Ⅲ 7階
高橋彰税理士事務所
電話番号03-5207-5760
代表取締役、代表税理士高橋彰
交通
有楽町線麹町駅より徒歩1分
半蔵門線半蔵門駅より徒歩5分
JR/丸の内線四谷駅より徒歩13分
料金表
相続の専門性を活かした業界最安クラスの料金水準
相続税申告
基本料金
| 遺産総額 | 申告料金 |
|---|---|
| ~4千万円 | 13万円(税込14.3万円) |
| ~5千万円 | 18万円(税込19.8万円) |
| ~6千万円 | 23万円(税込25.3万円) |
| ~7千万円 | 28万円(税込30.8万円) |
| ~1.0億円 | 38万円(税込41.8万円) |
| ~1.5億円 | 53万円(税込58.3万円) |
| ~2.0億円 | 68万円(税込74.8万円) |
| ~3.0億円 | 98万円(税込107.8万円) |
| 3.0億円以上 | 別途お見積り |
「遺産総額」は借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者特例、生命保険非課税控除を行う前の遺産額です。
加算報酬
| 土地 (1利用区分につき) |
5万円(税込5.5万円)~ |
|---|---|
| 非上場株式 (1社につき) |
15万円(税込16.5万円)~ |
| 相続人が2名以上 | 基本報酬額×10%×(相続人の数―1) |
お見積もり提示に詳細のご説明を致します。
その他の報酬
| 不動産評価に必要な資料の取得代行・旅費交通費 | 実費 |
|---|---|
| 金融機関残高証明書の取得代行等 | 別途お見積り |
| 遺産分割協議書の作成(簡易) | 別途お見積り |
| 税務調査の対応を行う場合 | 日当5万円(税込5.5万円) |
※司法書士、弁護士等のご契約が必要な場合は別途となります。
よくある質問
よくあるご質問を挙げています。ご不明なことはお気軽にご相談ください。
-
事務所に行くことが難しいのですが、他の対応はできますか。
専任の担当者がご自宅などにお伺いさせていただきます。
郵送、お電話、メールの他に、Zoomも対応可能ですので申し付け下さい。 -
「相続手続き」とは何がありますか。
身近な方が亡くなれば、誰しもその財産を引き継ぐ作業が必要となります。
仮に相続税申告が明らかに要らない方であっても、そうした手続きは必ず必要になります。
遺言書の確認、相続人を調べる、財産の確定、分割協議、名義変更そして相続税等の申告納税。
大きく分けるとこのような手続きがあります。 -
会社員のため平日休むことができず、申告判断前の手続きからお願いしたい。
手続きのために平日休めない、役所の手続きが大変、遺産の種類が多く大変、
このような方は沢山いらっしゃいます。
私どもはこのような申告前の相続手続きからサポートを行っています。
主なものとして、①相続人調査、②必要書類の取得代行、③相続財産の調査、④相続関係説明図の作成、⑤遺産分割協議書作成、⑥不動産の名日変更(司法書士連携)、⑦預貯金等の解約名義変更などが挙げられます。 -
遺産分割がもめそうで、これをうまくまとめてくださることはできますか。
対応可能です。当センターは相続経験の豊富な税理士が担当し分割協議から関わることが出来ますし、トラブルが予想されるケースは弁護士と連携して対処いたします。
分割協議がまとまりませんと最終的な申告が終わらず、また分割次第では相続税も大きく変わってしまいます。双方の綿密な連携により遺産分割を進めていきます。 -
相続人に認知症の相続人がいるのですが、遺産分割協議で何か手続きは必要ですか。
相続人の中には認知症で判断能力が十分でない方がいらっしゃいます。このような方は遺産分割協議には参加せず、代わりに成年後見制度を利用し、成年後見人が代わりに分割協議に署名捺印します。
認知症以外でも知的障害や精神障害の方も同様になります。
守秘義務が完全に守られますので、詳細はお気軽にご連絡ください。 -
認知症の親の財産を管理する方法の「家族信託」とはどういったものでしょうか。
お亡くなりになる前の生前対策のひとつとして、家族信託が注目を集めています。家族信託とは例えば認知症の親の財産を子供が管理する方法の一つです。
財産内容と財産を委託する委託書(親)と託される受託者(子)を明記した信託契約書を作成し公証役場で公正認書にするやり方を取ります。
詳細はお気軽にご相談ください。 -
知り合いで相続税の納税がなくて安心したら、その後の相続で大変な税金がかかったと聞きました。
これはどういうことでしょうか。例えば、お父様がお亡くなりになった際にお母様に配偶者軽減特例を使うケースがあります。この特例は1億6千万円まで使うことが出来て、その分税金がかからなくなる制度です。
勢い最大限まで配偶者に遺産分割したくなりますが、そのお母様が亡くなった時は配偶者がいませんのでその財産全額が課税財産として子供などに相続され、かつ相続人も少なくなることから、多額の税金がかかる結果となります。
お父様の相続の際に子供などに財産を相続すれば、お父様(一次相続)とお母様(二次相続)合わせてトータルの税金に大きな差が出るわけです。
こうした二次相続も考えられる税理士を是非とも専任すべきでしょう。 -
準確定申告とはどういったものでしょうか。
お亡くなりになった方が生前個人で事業や不動産貸付をされていた場合に、1月1日からお亡くなりになった日までの所得税や消費税の確定申告を準確定申告と言います。
お亡くなりになった日から4か月以内に申告納税が必要となります。
当センターはこの準確定申告の対応もお受けしています。 -
相続税申告を済ませましたが、不動産が不整形地のため相続税評価額が過大に申告したのではないかと思います。申告後の修正は可能か、またそうした再検査や修正申告の手続きはお願いできますか。
相続税申告において、不動産や非上場の株式の評価はとても複雑な計算を行い、またその判定方法も捉え方によって大きく変わるところがあります。
ご質問の不整形地の評価では不整形地補正率や速報路線価影響加算率などが正しく計算されているか、再検査が必要だと思われます。
一度出した申告による納税額が過大であった場合は、正しくは「更正の請求」を通じて還付手続きを行うことが出来ます。
当センターは相続専門の税理士が担当して、このようなご依頼にも応じています。
一度出した申告内容で少しでも不安なことがあれば、お気軽にご連絡をください。
ご相談の流れ
-
01初回面談
初回ご面談は無料です。お客様のご自宅へのご訪問、オンライン、お電話などご希望に合わせてご対応いたします。
面談後は面談内容に沿った内容での相続レポートをお渡しします。 -
02ご契約
提案内容のご了承をいただきましたら、業務契約を交わします。
-
03必要書類の収集
戸籍謄本、残高証明書、不動産評価資料など、相続税の申告に必要な資料の収集をサポートいたします。
-
04準確定申告
不動産収入がある場合や年金が一定額以上ある場合に「亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間」
の所得税申告を行います(亡くなった日から4ヶ月以内に申告が必要です)。 -
05財産目録作成
資料の収集から1~2か月程度で財産目録を完成させます。
財産評価の説明に加えて過不足の有無をご確認していただき、財産目録が確定します。 -
06遺産分割
確定した財産目録に基づいて遺産分割の協議をします。この際に「二次相続」を考慮した遺産分割シミュレーションのご提案を致します。
遺産分割が確定しましたら、遺産分割協議書を作成いたします。 -
07相続税申告書の作成
財産目録、遺産分割協議書に基づき、相続税の申告書を作成いたします。
-
08ご署名・ご捺印
相続人様全員にお集まりいただき、遺産分割協議書、相続税申告書等へのご署名、ご捺印をいただきます。
遠方の相続人様などで当センターまでお越しいただけない場合には、訪問、郵送でも対応が可能です。 -
09相続税申告書の提出と相続税の納付
作成した相続税申告書は、当センターにて責任をもって税務署に提出いたします。
なお相続税の納付については、お客様にお願いしております(亡くなった日から10ヶ月以内に納税が必要です)。 -
10申告書の控えとお預かり資料をご返却
税務署に提出した申告書の控えを製本して、お預かりした資料とともにご郵送します。
-
11各種名義変更手続き
お客様に代わり、不動産、預金等の名義変更手続きをいたします。不動産の相続登記については専任の司法書士
が対応し、その他の財産の名義変更については当センターにて代行できます。
サービスパンフレット
万全の生前対策から
相続税の申告手続き、相続後の資産運用まで
オールインワンで相続専任の税理士がしっかりとお客様を支えます。
3つの大きな柱となるサービスを分かりやすくパンフレットでご紹介いたします。